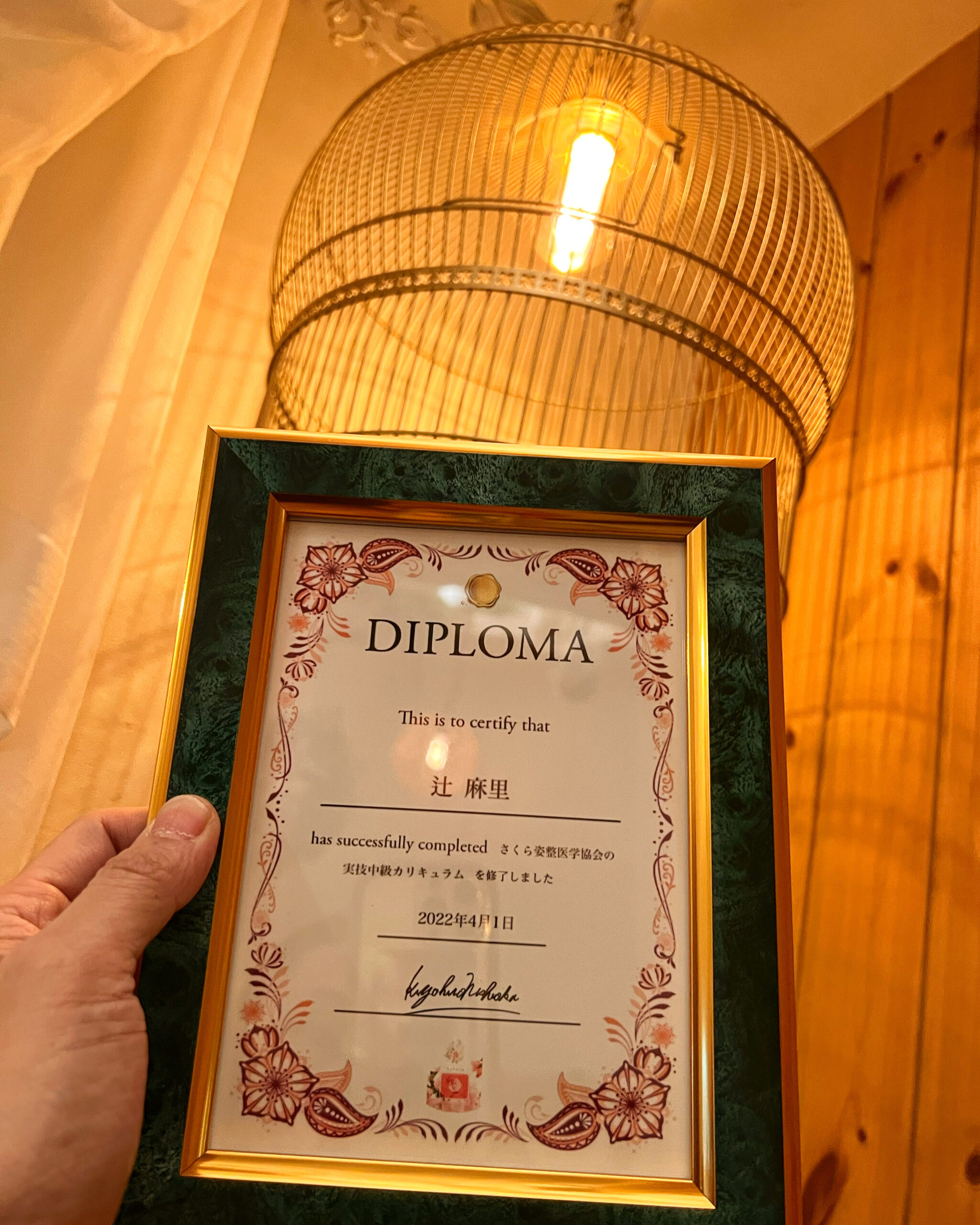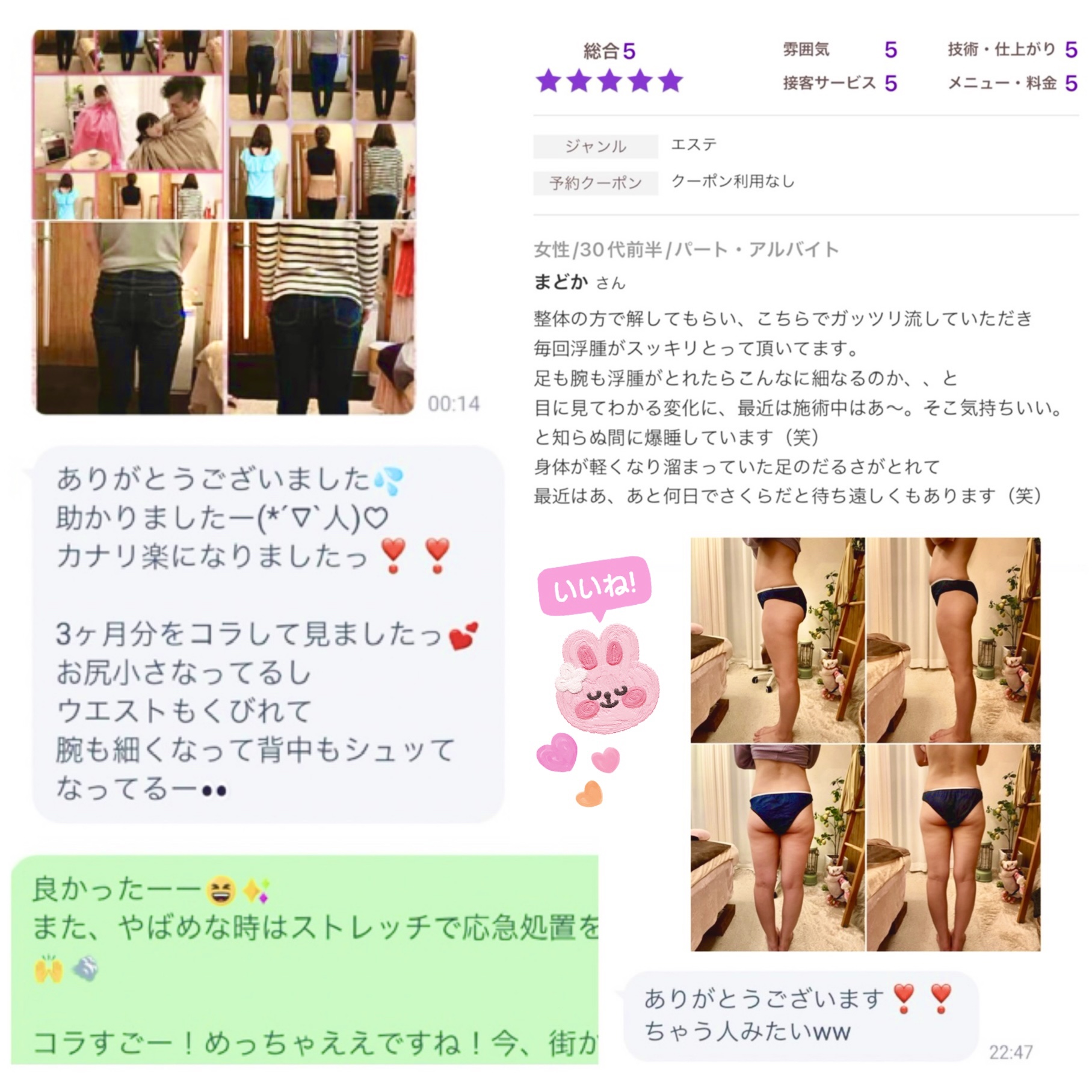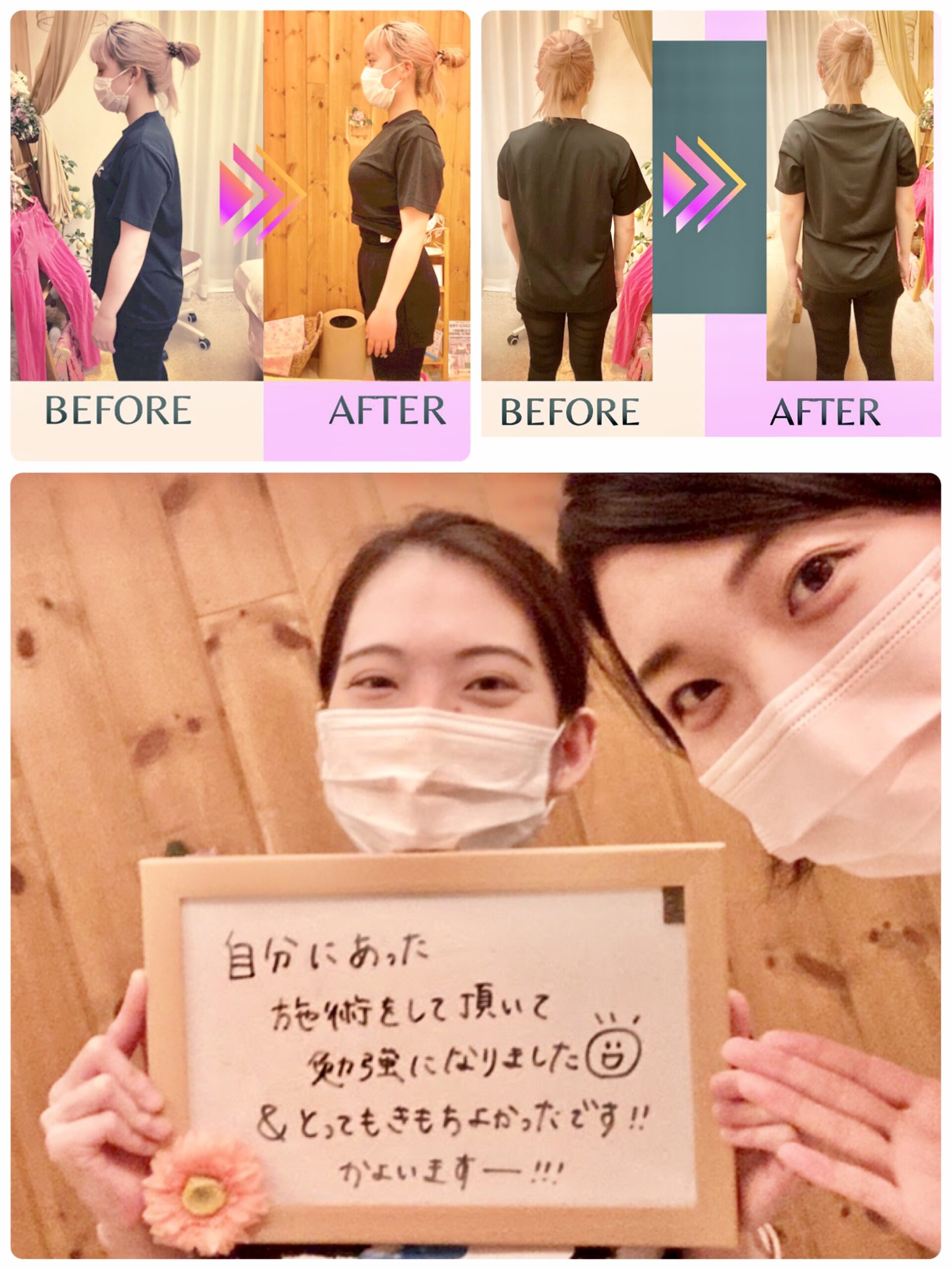🌸江戸時代 vs 現代の女性生理事情🩸
~生理の意味・回数・捉え方がどう変わったのか?~
📜【1】江戸時代の女性たちは「生理をコントロールしていた」?
よく語られる話に、
「江戸時代の女性は生理を自分で止めたり、トイレで排出したりしていた」
というものがあります。
これは完全な“都市伝説”ではなく、ある程度の身体的コントロール力(骨盤底筋・腹圧調整)を持っていた可能性があります。
✔️背景にはこんな理由があります:
| 要因 | 解説 |
|---|---|
| 🍚 栄養状態が今より低い | ホルモンが安定せず、生理が自然と軽くなっていた可能性も |
| 🧘♀️ 体をよく動かしていた | 骨盤底筋や腹筋群が鍛えられており、経血コントロールが無意識にできていた説も |
| 🚽「月経血コントロール法」 | 昔の東洋医学やヨーガにも類似の方法があり、トイレで排血する「経血コントロール」文化もあった |
つまり、「布ナプキンがなかったから垂れ流していた」と思われがちですが、実際は経血を受け止める布+ある程度の排血タイミングの意識があった可能性があります。
⏳【2】生涯の生理回数の差がもたらすもの
🏯江戸時代の女性(生理回数:平均100回以下)
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 初潮:15歳前後 | 栄養状態や身体の成熟が遅め |
| 妊娠・授乳の連続 | 妊娠中・授乳中は生理が止まる=排卵が抑制される |
| 子だくさん(平均5人) | 出産のたびに生理の「休憩期間」が長くなる |
| 平均寿命50歳未満 | 閉経前に寿命が訪れることも多かった |
🏙現代女性(生理回数:約450回)
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 初潮:12歳前後 | 栄養状態・生活環境の変化により早まった |
| 出産回数が少ない | 1~2人、または未出産の人も多い |
| 妊娠・授乳期間が短い | 長期的に排卵・月経を繰り返している |
| 平均寿命80歳以上 | 50歳までには多くの生理が積み重なる |
🧬【3】生理回数が多いとどうなるのか?
🔥毎月の排卵=“卵巣の小さな炎症”とされる
- 排卵は、卵巣から卵子が飛び出す**微細な「出血」や「組織損傷」**を伴います。
- これが年に12回、約35年間も繰り返されると…
→ 卵巣がん・乳がん・子宮内膜症などのリスクが高まる。
🧠生理の多さ=女性の強さの象徴ではなく、ホルモンと内臓への“負荷”が蓄積されている状態でもあります。
💡【4】では、どうしたらいいの?
🍃現代女性が学ぶべき知恵とケア法:
| 学ぶこと | 実践法 |
|---|---|
| 昔の女性の身体との向き合い方 | 骨盤底筋エクササイズ・経血コントロールへの意識 |
| 排卵回数を抑える | ピルなど医療的対応も含め、生理の“質”に目を向ける |
| 月リズムを感じる生活 | メラトニン・自律神経・ホルモンの自然調整を意識する |
| 無理な我慢をしない | 「甘え」ではなく、適切に休む権利を大切にする文化づくり |
🌸まとめ:女性の体は時代とともに変わる
- 江戸時代と現代では、女性の体・生理・環境・生き方すべてが違います。
- 生理は、女性が「命を育む準備をし続けている」証。その負荷を知り、ケアし合う社会が必要です。
- 古き知恵(経血コントロール・月との調和)と、現代の医療的ケア(ホルモン治療・ピラティス整体)をバランスよく活かすのが理想です。