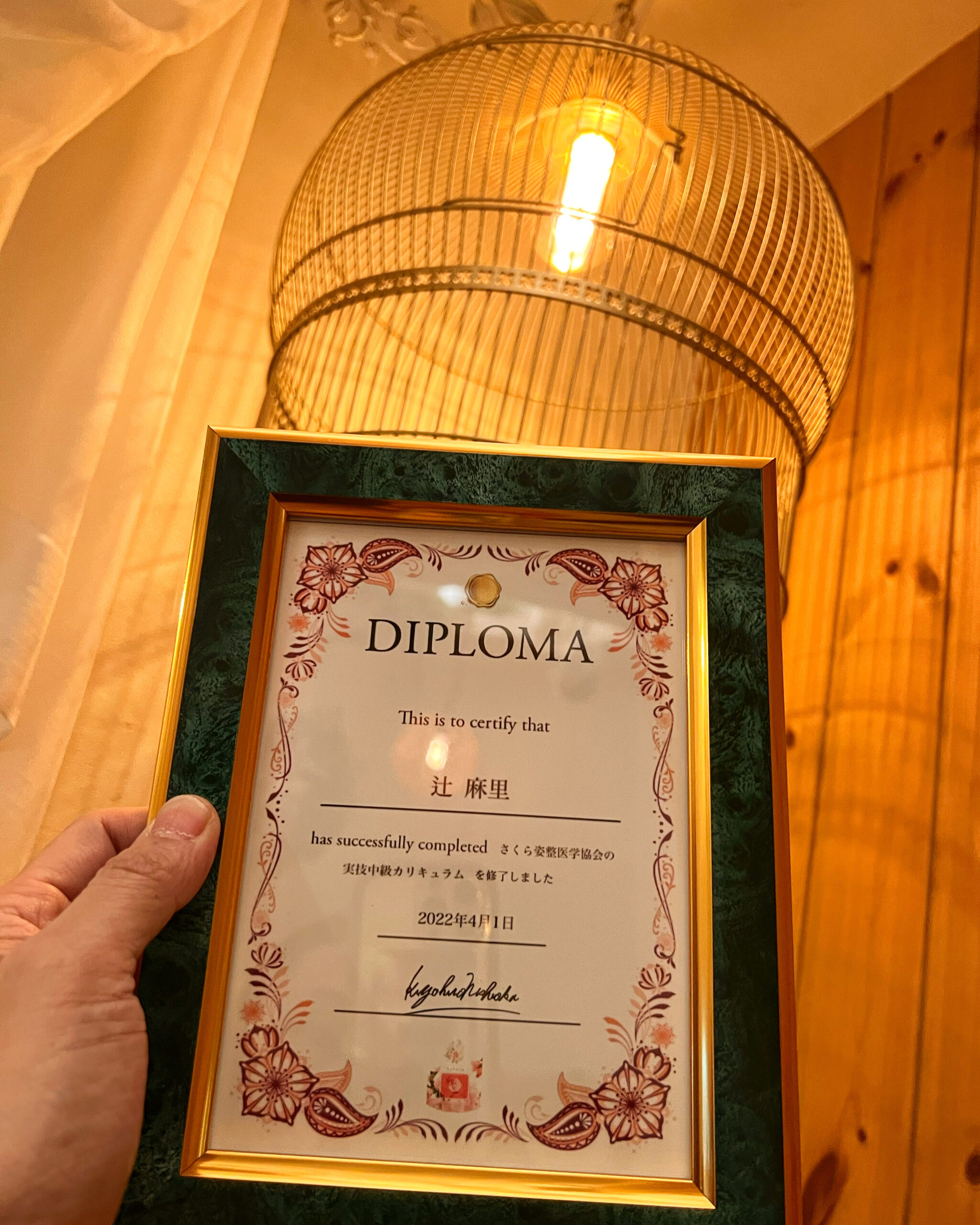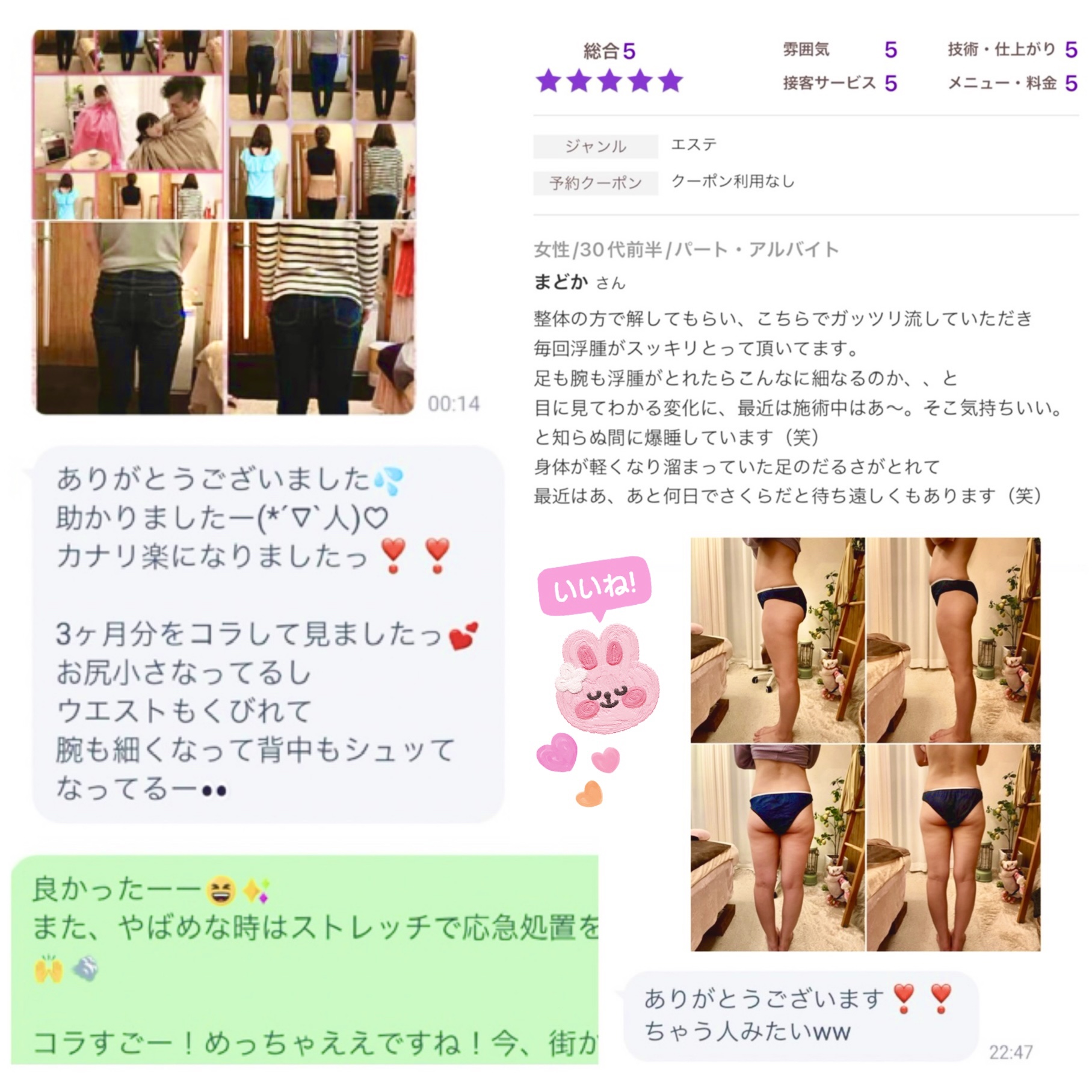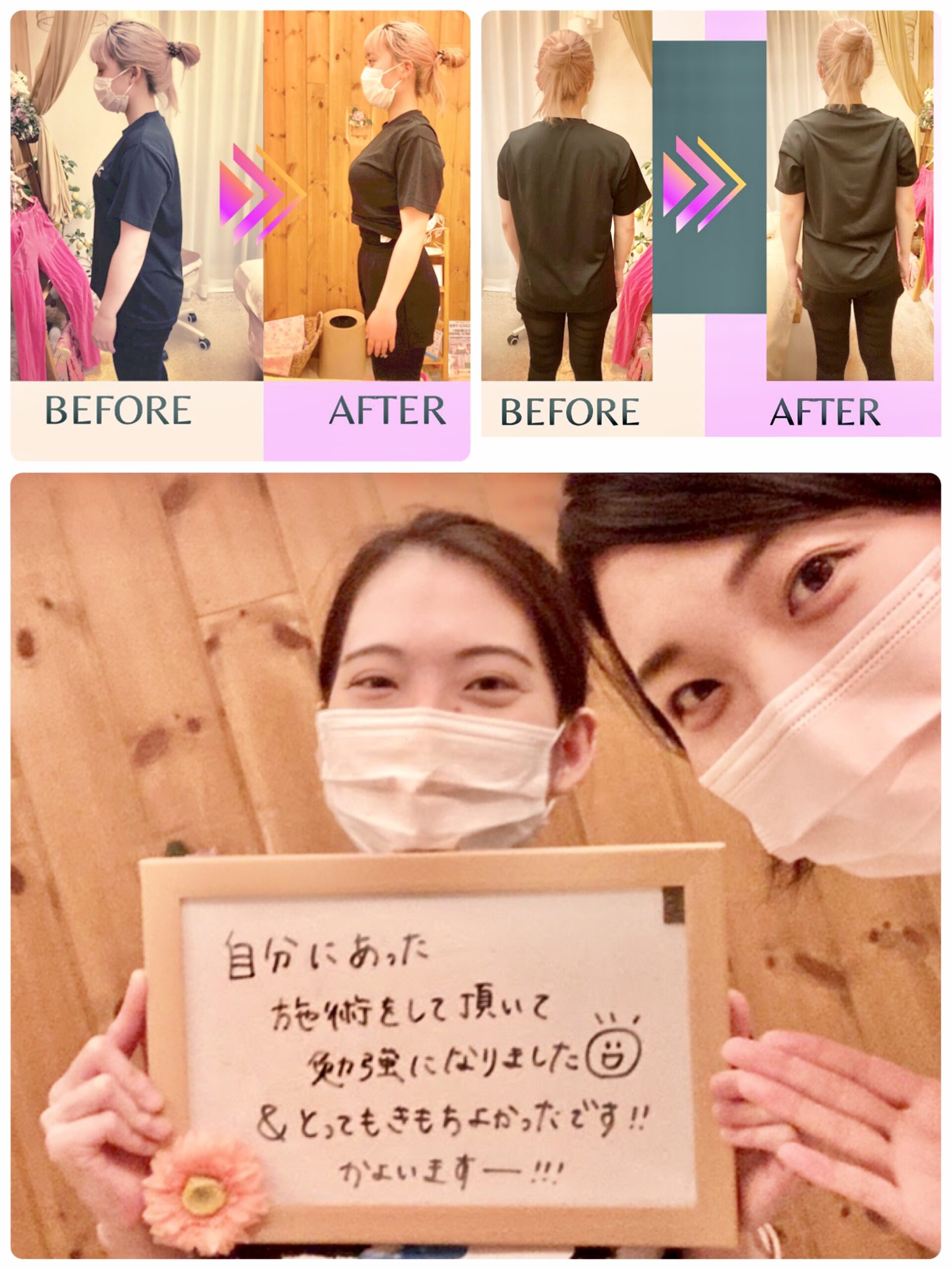女性同士の「周期の連鎖」は進化的な名残?
- 一斉に排卵・出産できれば「オスを分散できる」→性的競争の回避
- 同時に子育てすれば「協力しやすい」→生存率アップ
実際に「女性の生理周期が周囲の女性と同期することがある」という話は、昔から民間でも科学の分野でも語られてきました。これを「月経同期説(menstrual synchrony)」と呼びます。代表的な研究は1971年のマルサ・マクラントック博士によるものですが、後年に再現性が低いことが分かり、科学的には否定的な見解が強くなっています。
🌕では、なぜこのような「連鎖」や「満月」との関係が語られるのか?
① 満月と生理の神話的関係
生理周期(平均28日)は月の満ち欠けの周期(約29.5日)にとても近いため、人間も月のリズムに影響を受けているという考えが古くからあります。
このことから「満月に生理が重なる人が多いのでは?」という印象が生まれたと考えられます。
② においによる生理同期?(フェロモン説)
前述のマクラントックの研究では、「女性同士のフェロモン(におい)」が脳下垂体に影響し、排卵や月経周期を調整する可能性があるとされました。しかしこれは再現性に乏しく、現在は科学的に証明されたものではありません。
🔍それでも「連鎖」のように感じる理由
✅ 偶然の一致
28〜35日の範囲で多くの女性が月経を迎えるため、数人が集まれば誰かの周期と一致する確率が高くなります。
✅ 共有生活の影響
共同生活(寮・家族・チームなど)では、食事・睡眠・ストレス・光環境などが類似し、結果的にホルモンバランスが似てきて、周期が「近づく」可能性もあります。
🧬では、「生存確率を上げるための連鎖」説はどうなの?
これは進化心理学的な視点から考えることができます。
🦍仮説:集団出産による育児協力
一部の動物では、集団で同時期に出産・授乳することで、育児や子どもの防衛を助け合う利点があります。
もし人間の祖先にもこうした性質があったとすれば、生殖のタイミングを揃えることは、子の生存率向上につながった可能性は否定できません。
しかし現代人では、環境もライフスタイルも大きく変わっているため、この仮説は魅力的でも証明には至っていません。
🌸結論(要約)
- 生理が「連鎖する」と感じるのは、周期の偶然や共同生活の影響である可能性が高いです。
- 満月との関係も、周期が似ていることから神話的に語られる傾向があります。
- 「生存確率を上げるため」という説は、進化論的に面白いですが、現代の科学では未証明です。